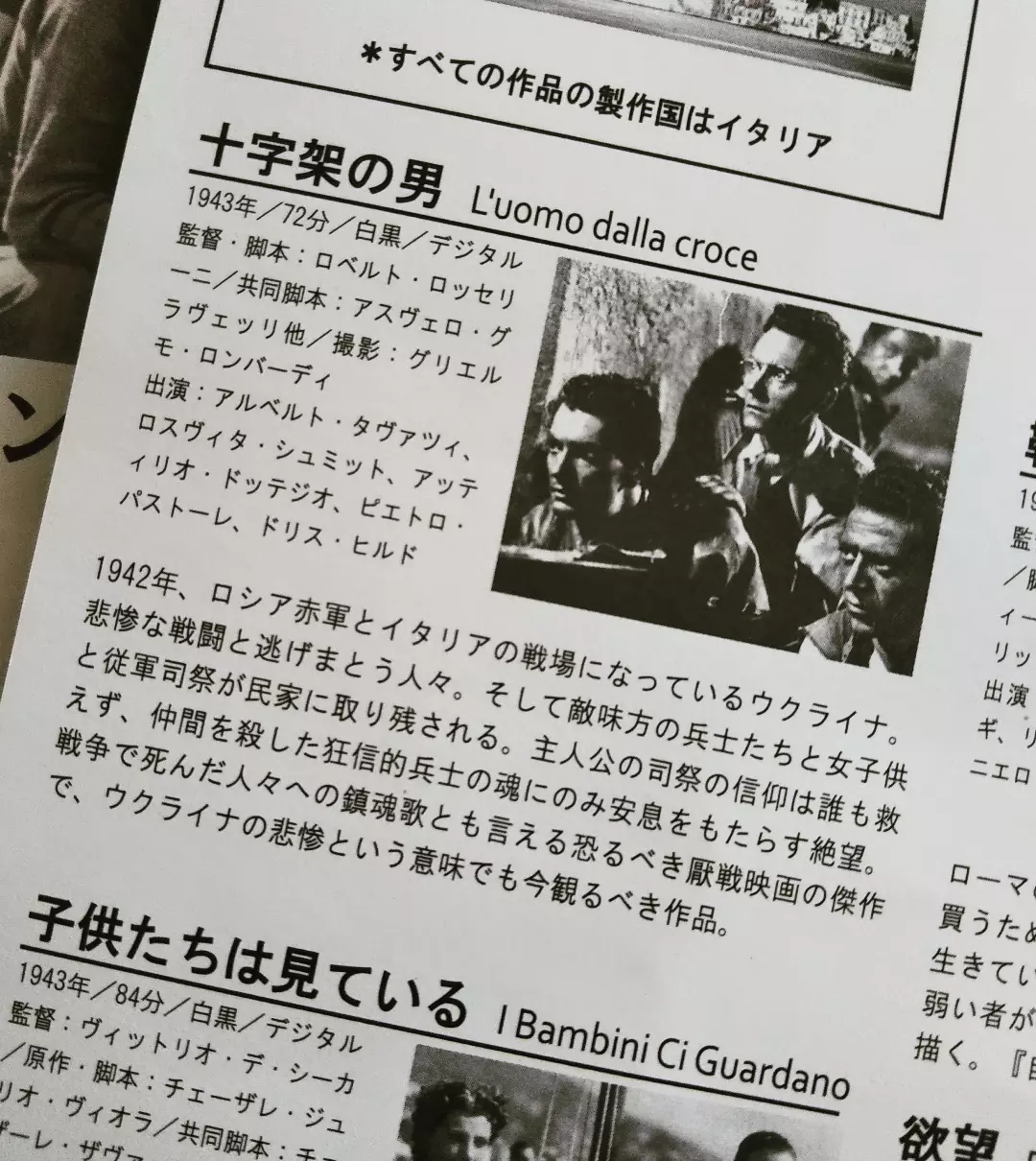フランス海軍の将校として初来日した明治十八年。寄港したナガサキを舞台に、夏から初秋にかけての“現地妻“お菊さんとの暮らしを通して、ナガサキの、ひいては日本の当時の姿を、日記形式の物語として描いた作品。
少し前に、この続編とも云える、同じ年の秋から冬にかけての、京都、日光、東京(江戸)などの散策集をまとめた『日本の秋』を読みまして、これが本当に素晴らしく。
そして、前後しましたが、ようやくの『お菊さん』です。
異国の地の慰みとして、金銭での割りきった関係とは予想しつつ、ちょっとした出会いのロマンスでもあれば、そして、お互いの激しい愛憎でも生じれば、大衆受けの小説として、はたまた戯曲やらカツドウとしてもてはやされるのでしょうが、当時の当地では“現地妻“斡旋はシステム化されており、その後も特に新たな愛情がわくこともなく、ただ淡々と日々の暮らしが、はじめて目にする不思議な日本の人々、住まい、風俗が描写されるのみ。
お菊さんへの様々な言及も、その不思議な日本人の描写の一環であるにすぎず。
それでもね、最後のお菊さんとの別れのシーンは、淡々と描かれているからこそ、逆に何かミョーにジーンとくるんですな。
『日本の秋』の感想の繰り返しになりますが、一世紀半という時の隔たり以上に、ロチという異国人の目を通して描かれるためか、当時の我が国が、本当に幻想的に感じられ。
モノの本などで若干の知識があっても、実際に訪れてみて、最後まで本質的には交われなかったロチにとっての日本。
それでも、折に触れ思い出すであろう、キモノに包まれた人形(ブウベ)のごときムスメ達、どこまでも白き畳、やむことなき蝉の声、気だるき三味線(ギタル)の音、遠くに響く寺の鐘、、、
我々日本人にとってもいずれは、ロチのような異国人の目に映る如く、これらは幻影となっていくのだろうか? 春をひさぐ女のみが生きながらへ。
(明治十八年当時、長崎のお坊さんがすでに、フランスの「同業」である修道士が造った二大リキュール、ベネディクティンとシャルトリューズを嗜んでいたとはね。ちょっとビックリ)